
|
|
紅の貴婦人 第一話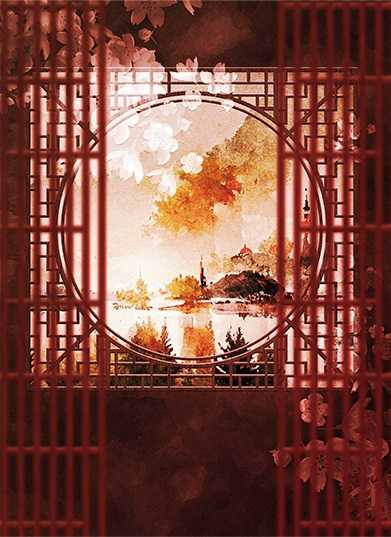 画像は、てんぱる様からお借りしました。 海斗が両性具有設定です、苦手な方はご注意ください。 シャラシャラと、風に揺れる度に花嫁を乗せた輿に飾られた宝石が揺れた。 「大層立派な花嫁行列だこと。」 「そりゃぁ、なんていったってあの紅家の輿入れ行列だからねぇ。」 「紅家って?」 「あんた、知らないのかい?紅家って今や飛ぶ鳥を落とす勢いの名家だよ。」 「それじゃ、輿に乗っているのは、紅家のお姫様かい?」 「まぁね・・」 花嫁を乗せた輿は、やがて宮城の中へと入っていった。 (もう、後戻りは出来ない。) 花嫁―海斗は、後宮に入る一月前の事を思い出していた。 「海斗、奥様がお呼びよ、早く来なさい!」 小鳥の囀る声を聞きながら海斗が眠い目を擦り自分の部屋から出ると、廊下には紅家の長女・愛齢の姿があった。 「あら、お前もお母様に呼ばれたのね?」 「ええ・・ 「ふん、相変わらず可愛げのない子。まぁいいわ、お前が嫁いだらその鬱陶しい顔を見ずに済むのかと思うとせいせいするわ。」 「え・・」 「まぁあなた、何も知らないのね。」 愛齢はそう言って意地の悪い笑みを浮かべると、自分の部屋へと戻って行った。 「来たわね。」 「はい・・」 紅夫人は、ジロリと海斗を睨みつけると、次の言葉を継いだ。 「急な話だけれど、お前にはあの方の元へ嫁いで貰うわ。」 「あの方?」 「青天君よ。」 青天君―この国でその名を知らぬ者は居ない。 穢れを背負った皇太子にして、狂人。 青天君の元にはこれまで何人もの娘が嫁いだが、皆生きて故郷に戻って来る事はなかった。 そんな恐ろしい彼の元に、何故自分が嫁ぐ事になったのか―海斗がそんな事を思った時、紅夫人は茶を一口飲んだ後、こう言った。 「青天君が、お前をお望みなのよ。」 「わたしを、ですか?」 「えぇ・・」 紅夫人は、愛齢が皇太子妃と周囲から期待されていたのだが、青天君が選んだのは、海斗であったのだと彼女は話した。 「どうして、俺が・・」 「あなたを、見初めたのですって。」 「見初めた?青天君が、俺を?」 「打毬大会で、あなたの勇姿を見たんですって。」 紅夫人の言葉を聞いた海斗の脳裏に、ある記憶が甦って来た。 それは、海斗が十五になった時の事だった。 「打毬大会?」 「ええ、あなたも参加して欲しいの。」 「わかりました。」 愛齢が打毬大会に出場する筈だったのだが、大会当日彼女は熱を出してしまった。 彼女の代役として、海斗が大会に出る事になった。 「俺に上手く出来るでしょうか?」 「大丈夫よ、自分を信じて。」 その大会で、海斗は優勝した。 競技中、海斗は天幕の中から誰かの視線を感じた。 美しい金髪が時折、天幕から少し垣間見えていたが、もしかしてその持ち主が青天君だったのだろうか。 「お義母様・・」 「海斗、許しておくれ、わたしは・・」 「今まで血が繋がらないわたしを育てて頂き、ありがとうございました。」 紅夫人は、涙を流しながら海斗を抱き合った。 こうして、海斗は青天君の元へ嫁ぐ事になった。 「まぁ、素敵!」 鮮やかな真紅の婚礼衣装を身に着けた海斗を見て、侍女達はそう言って溜息を吐いた。 紅家は都に屋敷を構えていたので、海斗の花嫁行列は、すぐに終わった。 「お待ちしておりました。」 海斗が輿から降りると、彼女の前に数人の宦官達が現れた。 「何ですか、あなた方は?」 「わたくし達は、皇太后様の命で参りました。」 海斗は侍女達と共に、皇太后・呉妃が住まう冬宮殿へと向かった。 「お前が、紅家の養女か。美しい髪をしているね。」 「ありがたきお言葉、光栄にございます。」 「堅苦しい言葉遣いは止せ。妾もそなたと同じ炎の髪を持つ身。仲良くしようぞ。」 そう言って呉妃(エリザベス)は、海斗に優しく微笑んだ。 「ここが、紅妃様がお暮しになられる春宮殿です。」 宦官達に海斗が案内されたのは、美しい朱色の宮殿だった。 ―あれが、紅妃・・ ―禍々しい赤毛・・ ―あんな子が何故、青天君様の妃に? (これから俺、後宮でやっていけるかな?) 海斗からそんな事を思いながら蝶が舞う美しい庭を眺めていると、そこへ一匹の猫がやって来た。 「お前、何処から来たの?」 海斗がそう猫に尋ねると、猫は小さい声で鳴いて海斗に擦り寄って来た。 「ブラッキー、何処に居るんだ?」 その時、庭の向こうから、若い男の声が聞こえて来た。 美しく鮮やかな金髪、そして蒼い宝石のような瞳。 「あなたは・・」 「お前が・・」 青天君―ジェフリーはそう言って海斗を見つめると、海斗を抱きしめた。 「何すんだ、この・・」 「大人しくしろ。」 「え?」 ジェフリーがそう言って海斗を抱き締めて身を屈めると、木の幹に一本の矢が突き刺さった。 「ひっ・・」 「あらぁ、ごめんなさい。お怪我、ありませんでしたか?」 そう言いながらサラサラと衣擦れの音を立てながら現れた女人は、金色の瞳でジェフリーと海斗を見つめた。 (誰、この人?) 海斗がそう思いながら見知らぬ女人を見ると、彼女は開口一番、こう言った。 「あなたが、生贄ね?」 「え?」 「まぁ麗妃様、こちらにいらっしゃったのですね!」 「陛下がお呼びですよ!」 「では、わたくしはこれで。」 女人はそう言うと、風のように去っていった。 「あの人は・・」 「あぁ、あの女は、帝の寵妃さ。」 ジェフリーは素っ気ない口調でそう言うと、木の幹に刺さっていた矢を引き抜いた。 その矢には、こんな文がくくりつけられていた。 『皇太子の座をクン王子に譲れ。』 ジェフリーは文を破り捨て、溜息を吐いた。 クン王子は、帝の寵妃・麗妃が産んだ子で、まだ三歳になっていない。 その王子の後見人、即ち摂政として権勢を振うつもりなのだろうが、そうはさせない。 「あの人、変な事を言っていたけれど・・」 「気にするな。」 「うん・・」 ジェフリーは、海斗が髪に挿している簪を見た。 それは蓮を象ったもので、美しい真珠が簪の先についていた。 「その簪は?」 「これは、実母の形見です。」 海斗は、そう言うと自分の生い立ちを話し始めた。 海斗は、生まれてすぐに紅家の正門前に捨てられていた。 紅夫人は、海斗を我が子同然に育て、教育を受けさせた。 しかし、海斗はずっと自分の居場所を探していた。 自分が居るべき場所はここではないと、いつしか思うようになっていた。 「実の母親に、会いたいと思った事は?」 「わかりません。」 「そうか。」 「失礼致します、皇太子様。麗妃様から、お手紙を預かりました。」 「ありがとう。」 ジェフリーは麗妃付の女官から手紙を受け取ると、そこには今夜七時に開かれる宴に出席せよというものだった。 「宴って、俺も出ていいの?」 「あぁ。」 (あの女が一体何を考えているのかはわからないが、何か起きた時にはこの子を守ってやらねば。) 「宴に出るといっても、お前は何が出来るんだ?」 「琵琶と箏が出来ます。」 「そうか。」 「いずれ後宮に上がる日が来るかもしれないからと、義母に専属の家庭教師をつけて貰いました。」 「それは良かった。」 ジェフリーと海斗がそんな話を春宮殿でしている頃、麗妃―ラウルは琵琶を奏でながらあの赤毛の娘の事を思い出していた。 (あの娘、何処かで見たような・・) 「麗妃様、どうかなさいましたか?」 「いいえ、何でもないわ。それよりも、今夜の宴が楽しみね。」 「はい。」 その夜、ラウルが住まう麗宮殿で、華やかな宴が開かれた。 宴に集まった美女達は、それぞれ歌や舞で貴族達を楽しませていた。 「麗妃様、今日はあの方はいらっしゃらないのですか?」 「ええ。あの方は、気分が優れないようで・・」 「まぁ・・」 ラウルが取り巻き達とそんな話をしていると、突然池の方から美しい笛と琵琶の音色が聞こえて来た。 池に浮かんでいる舟には、青天君と紅貴妃の姿があった。 「あの方が・・」 「素敵な方ね。」 (やってくれたわね、ジェフリー。わたくしに逆らうつもりなのね!) 「素晴らしい演奏だったわ。皆さん、ご紹介するわね。こちらの方が、春宮殿に本日入られた紅貴妃様よ。」 ラウルの言葉を聞いた宮女達の視線が、一斉に海斗へと向けられた。 (え・・) ―まぁ、何て事・・ ―春宮殿ですって? ―あの・・ 「皆さん、そんなに睨まないであげて、紅貴妃様が怯えているでしょう?」 「ですが紅貴妃様が・・」 「黙りなさい。」 「申し訳ありません・・」 「さぁ皆さん、宴の続きをいたしましょう。」 ラウルはそう言って手を叩いた。 宴は深夜まで続いた。 「貴妃様、お帰りなさいませ。」 「ただいま。」 海斗の侍女・春桃はそう言うと、海斗の髪を優しく梳いた。 「ねぇ、春桃は後宮に入って長いの?」 「ええ。もう十年になります。」 「宴の時、皆俺の方を見ていたけれど・・何か、ここにはあるの?」 「春宮殿は、呪われているという噂がありますわ。」 「呪われている?」 「ええ・・」 春桃が言うには、その昔帝から深い寵愛を受けた妃が居たという。 だがその妃は、美しく聡明であったが故に、他の妃達から嫌がらせを受け、池に身を投げたのだという。 それから、春宮殿に嫌がらせをしていた妃達が次々と謎の死を遂げた。 「へぇ・・」 「その妃の魂が、今も彷徨っているという噂です。」 「そうなの。」 海斗が寝室で眠っていると、外から女の泣き声が聞こえて来た。 だが海斗は気の所為だと思い、そのまま眠った。 「おはようございます、貴妃様。」 「おはよう。」 「昨夜、不気味な女の泣き声が聞こえていませんでしたか?怖くて堪らなくて眠れませんでした。」 「そう?やっぱり、あれ気の所為じゃなかったんだ。」 「恐くないのですか?」 「幽霊よりも生きている人間の方が怖いじゃん。」 「まぁ、そうですわね。」 「ねぇ、俺はこれから何をしたらいいの?」 「今日は余り忙しくないので、好きな事をゆっくりなさって下さい。」 「わかった・・」 そう言ったものの、海斗は何もする事がなくて春桃が去った後、溜息を吐いた。 琵琶を中庭で奏でていると、茂みの中で何かがまた動いた。 「そこに誰か居るの?」 「申し訳ありません!」 茂みの中から出て来たのは、一人の少年だった。 みすぼらしい服装をした彼の手足には、赤黒い痣のようなものがあった。 彼は、海斗に英明と名乗った。 英明は、宮城の外にある街で暮らしており、幼い弟妹達の腹を満たす為に、宮城へ盗みに入ったのだという。 「春桃、この子に食べ物を持たせてやって。」 「貴妃様、ですが・・」 「哀れみはいりません。おいら、金は自分で稼ぎます。」 「英明、あなたはこれからどうしたいの?」 「おいら、来月には十になるんだけれど、何処の工房も雇ってくれないんだ。縫い物は女の仕事だから、男は駄目だって。」 そう言って英明は、唇を噛んだ。 「あなたは、裁縫が得意なの?」 「はい。死んだ父さんが、腕の良い職人だったんです。」 「春桃、筆と硯と紙を持って来て。」 「かしこまりました。」 海斗は紙に、紅家の知人で都一の工房の名を書くと、それを英明に渡した。 「この工房の主は、性別だけで職人を選ばないわ。一度行ってごらんなさい。」 「ありがとうございます!」 英明はそう言った後、海斗に頭を下げて春宮殿から出て行った。 「あれで、良かったのかな?」 「それは、わたくしにもわかりません。」 「そう。」 数日後、英明から文が届き、海斗が紹介してくれた工房で働き始めた事、親方や先輩達が優しくしてくれている事などが書かれていた。 「良かった。」 海斗は、安堵の溜息を吐いた。 「貴妃様、呉妃様がお呼びです。」 「わかりました。」 海斗が冬宮殿へと向かうと、そこには一人の少年の姿があった。 「貴妃よ、彼の事を憶えておるか?そなたの宮に忍び込み、生きる術を見つけた者じゃ。」 「英明、元気そうで良かった。」 「貴妃様のお陰で、おいらは道を踏み外さずに済みました。」 そう言った英明の顔は、輝いていた。 「婚礼、ですか?わたくしと、青天君様の?」 「そうじゃ。」 「わたくしは、お嬢様の代わりで後宮入りしたので、そんな・・」 「そなたの貴妃としての地位を確かなものにする為、皆にお披露目せねばならぬ。」 「はぁ・・」 呉妃は完全に乗り気のようで、断れる雰囲気ではなかった。 そして、呉妃の下、海斗の婚礼の準備が進められた。 ―まぁ、貴妃様が? ―それは、本当なの? ―青天君様の妃になられるなんて・・ 「麗妃様・・」 「放っておきなさい。」 「ですが、このままでは・・」 「放っておきなさいと言っているでしょう。わたくし達が騒いだりしたら、呉妃様に睨まれるのはわたくし達の方ですよ。」 「はい・・」 (やってくれましたね、呉妃様・・この借りは、必ず返しますよ。) 麗妃は、静かに笑うと、枯れた菊を花鋏で切り落とした。 「貴妃様、失礼致します。」 「どうしたの?」 「婚礼衣装をお届け致します!」 「まぁ、ありがとう。」 英明から受け取った真紅の婚礼衣装は、美しい鳳凰の刺繍が施されていた。 「素晴らしいわ。」 「初めての仕事だから、四日も寝ずに頑張りました!」 「それはいけないわ、すぐに休みなさい。」 「はい。では、おいら・・わたしはこれで失礼致します、貴妃様。」 英明はそう言って頭を下げると、春宮殿から去っていった。 「貴妃様、呉妃様からお祝いの品が届きました。」 「まぁ、呉妃様から・・」 海斗は、美しい螺鈿細工が施された琵琶を撫でると、それを爪弾き始めた。 「誰か、誰か来てぇ~!」 「池から、死体が・・」 「誰か~!」 海斗が、騒ぎが起きている池の方へと向かうと、そこには一人の宮女の遺体が浮かんでいた。 「一体、どういう事なの?」 「貴妃様・・」 「あの子が、足を滑らせてしまって・・」 宮女の遺体は、すぐさま衛士達によって池から運ばれていった。 「呉妃様、このような事が起きたので、婚礼は延期した方がよろしいのでは?」 「ならぬ。」 「まぁ、死んだのはわたくしの侍女ですのよ。それなのに、弔いをわたくし達にさせないなんて!」 そう叫んだ麗妃は、袖口で顔を覆ってわざとらしい声を出しながら泣き始めた。 ―なぁに、あれ? ―みっともないわねぇ。 「そなたが何を言おうと、婚礼は予定通りに行う。」 呉妃は有無を言わさぬ口調でそう言うと、そのまま去っていった。 (このままでは、済ますものですか!) 幼子の泣き声が聞こえ、ラウルが気怠そうな様子で庭の方を見ると、そこには泣き叫ぶ我が子の 姿があった。 クン王子は、転んで膝を擦り剥いていた。 「母上・・」 「英蘭、この子を部屋へ連れて行きなさい。」 「はい!」 泣く我が子をあやしたり抱き締めたりする事なく、ラウルは冷たく侍女にそう命じると、その場を後にした。 「そなた、クン王子に冷たくないか?」 「ええ、わたくしは敢えてあの子に冷たくしているのです。無駄に甘やかしては、あの子の為にはなりませんもの。」 「それはそなたの経験談か?」 「ご想像にお任せ致しますわ。」 妓楼の一室で、ラウルはそう言うとかつて自分に懸想していた男にしなだれかかった。 「ここは、君にとっては懐かしい場所だろう?」 「雷様、意地悪な事をおっしゃらないで。」 ラウルは静かに酒を煽りながら、かつてここに売られて来た日の事を思い出していた。 「早く歩け!」 ラウルが生まれ育った国は、一夜にして滅びた。 貴族の娘として何不自由ない生活を送っていたラウルは、両親を殺され、最下層の奴隷として生きる事になった。 王都の近くにあったこの妓楼へと売られ、ラウルは辛酸を舐める日々を送った。 いつか、自分を虐げた者達に復讐してやるー内に激しい憎悪の炎を燃やしながら、ラウルは妓女としてその名を馳せた。 やがて、その噂を聞きつけた皇帝が妓楼に入り浸り、ラウルを後宮に入れた。 ―蛮族の女を後宮へいれるなど・・ ―世も末だ。 (何とでも言えば良い。) 皇帝を骨抜きにしたラウルは、やがてクン王子を授かった。 クン王子は、ラウルに似て病弱で、良く熱を出して寝込んでいた。 ラウルはそんなクン王子の教育を全て乳母に任せ、皇帝の子を授かろうと躍起になっていたが、中々授からない。 焦りをラウルが感じている中、自分と対立していた青天君が、妃を迎えた。 自分よりも若くて、美しい妃を。 (もしあの妃が陛下の子を宿したら・・わたしは・・) 「どうした、浮かない顔をして?」 「いいえ・・」 「そういえば、余り食べていないではないか?」 「ええ、少し胸焼けがして・・」 ラウルは、この頃月のものが二月程来ていない事に気づいた。 「すぐに医者を呼びましょう。」 「雷様・・」 妓楼時代からの知人・雷によって呼ばれた医師の診察を受け、ラウルは妊娠している事がわかった。 ―麗妃様がご懐妊ですって? ―まさか、陛下の御子なのかしら? 「貴妃様、いかがされました?」 「ねぇ、麗妃様が懐妊したというのは本当なの?」 「ええ。陛下は、大層お喜びのようで・・」 「そうなの。じゃぁ、産まれて来た子が、皇太子になる事はあるの?」 「それは有り得ませんわ。呉妃様がいらっしゃる限り。」 海斗は後宮の人間関係や権力構成などに疎い為、わからない事は春桃に聞いていた。 「呉妃様が一番後宮で偉いの?」 「はい。後宮の全権は呉妃様が握っておられます。呉妃様がご存命している間、あの麗妃様でさえ貴妃様には手出しできません。」 「そうなの。」 「それよりも、婚儀を明日に控えたご感想は?」 「そんな事聞かれても、実感が何だか湧かないというか・・」 海斗が春桃とそんな事を話していると、そこへ何処か慌てた様子の女官がやって来た。 「申し訳ありません、こちらにクン王子がいらっしゃいませんでしたか?」 「クン王子?見ていないけど・・」 「わたくし達が目を離している隙に、居なくなってしまったのです。」 海斗は、麗宮殿の女官達と共に、姿を消したクン王子を捜した。 クン王子は、冬宮殿で呉妃から刺繍を習っていた。 「クンは、筋が良いのう。」 「ありがとうございます。」 クン王子が懸命に針を動かしていると、そこへ海斗達が駆け付けて来た。 「クン王子、ご無事でよかった!」 「心配かけて、ごめんなさい・・」 クン王子を海斗達が麗宮殿へと連れて行くと、ラウルはクン王子の頬を平手で打った。 「母上・・」 「さっさと自分の部屋に戻りなさい。」 「今のはあんまりではないですか?」 海斗がそう言いながらクン王子を守ろうとすると、ラウルに蹴られた。 「誰に向かって口を利いているんだ、お前!」 「一体、何の騒ぎだ?」 「いいえ、何も。貴妃様がわたくしに無礼な口を利いたので、懲らしめてやっただけですわ。」 「陛下、わたしが悪いのです。わたしが・・」 「クン・・」 「クン王子、さぁお部屋へ参りましょう。」 クン王子の乳母・香蘭はクン王子を抱き上げると、その場を後にした。 「クン王子が可哀想。」 「麗妃様は、クン王子を自分が権力を持つ為の、“切り札”にしか思っていないのです。」 腹を痛めて産んだ子を蔑ろにするラウルの冷淡さを目の当たりにした海斗は、クン王子の事が気になって一睡も出来なかった。 ジェフリーとの婚儀を終え、海斗は後宮に入って初めて、彼と一夜を共に過ごした。 「貴妃様、おはようございます。」 「ん・・」 「昨夜は、“お楽しみ”だったようですわね?」 海斗の首筋から胸にかけて広がる薔薇色の痣を見た春桃は、そう言って新婚夫婦の寝室を後にした。 「クン王子は、どうして乳母に育てられているの?」 「体型が崩れるからと、麗妃様はクン王子に母乳をお与えになりませんでした。その頃、香蘭が我が子を死産し、クン王子の乳母として雇われました。香蘭は、麗妃様と幾度もクン王子の育児方針で対立していました。結局は、麗妃様がクン王子を手放してしまいましたけれど。」 「そう・・」 「クン王子は、とても良い子ですよ。ただ、病弱なだけで。」 実の親を知らない海斗だったが、紅家の令嬢として大切に育てられた彼女は、ラウルがどうしてそこまで実の子に冷淡になるのかがわからなかった。 「そういえば、ジェフリーのお母さんは?」 「とてもお美しい方だったと・・でも、青天君が三歳の頃にお亡くなりになられました。とても、惨い殺され方をされたと、噂では聞いております。」 「そんな・・」 「青天君は、貴妃様がいらっしゃってからは良く笑われる様になられました。青天君と貴妃様の間にお子様がお産まれになられたら、とても愛らしいお子様がお産まれになられるのでしょうね。」 「そんなの、まだ先だよ。」 ジェフリーと一夜を共にしてから二月が経った頃、海斗は謎の吐き気と倦怠感に悩まされていた。 「貴妃様、お粥をどうぞ。」 「ありがとう・・」 海斗が粥を一口食べようとした時、彼女は激しい吐き気に襲われた。 「貴妃様!?」 「何でもない・・」 「ですが・・」 海斗は椅子から立ち上がろうとした時、貧血がしてよろめいてしまった。 「誰か、薬師を!」 何処からか、泣き声がした。 海斗が泣き声のする方へと向かうと、そこには金髪碧眼の男児が居た。 ―どうしたの、坊や? ―かあさまを、捜しているの。 ―じゃぁ、一緒に捜そうか? ―ううん、もう大丈夫。 男児はそう言うと、海斗に抱き着いた。 「カイト、大丈夫か?」 「ジェフリー・・」 「貴妃様、ご懐妊おめでとうございます。」 医師はそう言うと、海斗に微笑んだ。 「本当に?」 「はい、間違いありません。」 海斗の妊娠を知った呉妃は、大層喜んだ。 「余り無理をするでないぞ。大切な時期だからな。」 「ありがとうございます。」 月満ちて、海斗が産んだのは元気な男児だった。 それと同時期に、ラウルも男児が産んだ。 「可愛いのう。」 「寝ていれば、可愛いのですけれどね・・」 そう言った海斗の両目の下には、隈が出来ていた。 「赤子は泣くのが仕事じゃ。と、言うても疲れが溜まるであろう。偶には王子を妾に預けて息抜きをするがよい。」 「ええ。それよりも、麗妃様は・・」 「彼女は、レイ王子にかかりきりだと聞く。レイ王子には、クンには与えなかった乳をやっているとな。妾は、クンが哀れに思うのじゃ。」 「呉妃様・・」 「青天君は、そなたが来てから変わった。どうか、これからも青天君を支えてやっておくれ。」 「はい!」 冬宮殿から春宮殿へと戻った海斗の元に、ジェフリーが何やら慌てた様子で駆け寄って来た。 「どうしたの?」 「さっき、こんなものが庭に投げ込まれていた。」 ジェフリーがそう言って海斗に見せたものは、紙に包まれた石だった。 その紙には、『王子を殺す』と書かれてあった。 「一体、誰がこんな事を?」 「それはわからない。ただ、警備の者を増やすように言おう。」 ジェフリーはそう言うと、海斗と息子を抱き締めた。 「陛下、申し上げます!国境付近にて敵軍が・・」 「何だと!?」 「陛下、青天君を国境へ向かわせては?」 「ならぬ。あやつは、余の・・」 「陛下、青天君にも武功を立てて貰わなくては、民があの者を皇帝として認める事が出来ましょうか?」 「うむ・・」 ラウルに言いくるめられた皇帝は、ジェフリーに出陣を命じた。 「そんな、リン王子が産まれたばかりだというのに・・麗妃様も酷な事をなさる。」 「だが、民の心を掴むには、青天君が戦場で武功を立てねば、あの方が・・」 海斗は、王子をあやしながらジェフリーが生きて自分達の元に帰って来てくれる事を祈った。 「カイト、そんな顔をするな。必ず帰って来る。」 「本当?」 「あぁ、約束だ。」 「これを、俺だと思って持っていて。」 「わかった。」 海斗から簪を受け取ったジェフリーは、それを大切そうに懐にしまった。 「リンを頼む。」 「うん・・」 出陣の日の朝、海斗はジェフリーと口づけを交わした。 「待っているから。」 ジェフリーが出陣してから数日後、春宮殿の女官達が皇帝の軍に捕らえられた。 「彼女達をどうするつもりなのです?」 「彼女達は、陛下に対して謀反を企てたのですよ。これは、許されぬ事ではないわ。」 「あなたが・・あなたが仕組んで・・」 「あらぁ、何の事?わたくしを疑うなんて、酷いわぁ。」 ラウルはそう言うと、海斗を見た。 「そうそう、ひとつだけあなたに伝えておきたい事があるの。次の皇帝になるのは、あなたの夫ではなく、わたくしの息子だとね。」 「そんな・・」 「貴妃様、申し上げます!呉妃様が、お倒れになられました!」 海斗が冬宮殿へと向かうと、女官達のすすり泣く声が聞こえて来た。 「呉妃様は?」 「先程、息を引き取られました。」 「そんな・・」 (これで、わたくしの邪魔者は居なくなった。) 呉妃の訃報を受けたラウルは、眠っているレイ王子を寝台から抱き上げた。 (安心しなさい、この国はいずれお前のものとなる。) レイ王子が父親に似た蒼い瞳でラウルを見つめた時、彼女の部下が部屋に入って来た。 「青天君を殺しなさい。」 「どのような方法で・・」 「戦場では、怪我がつきものよ。」 「かしこまりました。」 |